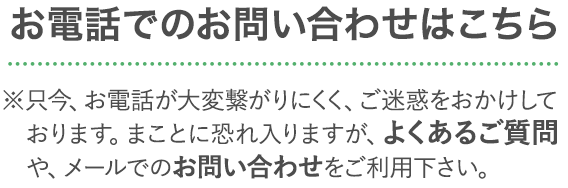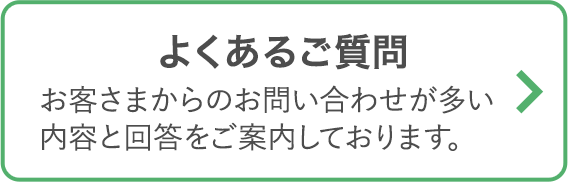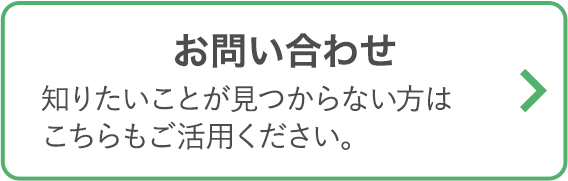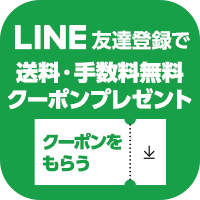楊さちこの季節のコラム
秋の夜長に「睡眠力」を養いましょう
2019.10.01

健康的な食事も運動もきちんとして、身体に気をつけようと努めている人は多いと思います。でも食事や運動よりずっと多くの時間を割いている睡眠。秋の夜長に見直してみませんか?
秋にこそ見直したい睡眠について
季節が秋に移り変わり、酷暑も一段落してきました。この季節にこそ、見直してほしいことがあります。それは、誰もが毎日欠かせない「睡眠」です。
夏は夜でも気温が高いため「寝つきが悪い」「寝苦しい」と途中で起きてしまうことも。一方で冬になると、夏とは逆に身体が冷えてしまって、朝起きても「寝足りない」ことがあります。その点秋は気候が安定しているので、「睡眠力」を養うのにぴったり。
実はこの過ごしやすい時期に、「睡眠力」をつけることで、夏の疲れを回復させ、厳しい冬に備えるための期間でもあります。
日本人は「あまり寝ない国民」と言われています。季節の関係で、なかなか寝つけなかったり、寝ていても疲れが取れない、ということはありませんか?
日本人の睡眠時間は欧米諸国に比べると短く、特に女性ではその傾向が顕著に表れているというデータがあります。また、厚生労働省のデータによると、現在、日本人の5人に1人は、睡眠時に何らかの障害を抱えているとされています。時間が不足しているばかりか、質にも問題があると考えられる睡眠。しかも睡眠不足は、健康維持にとって大敵なだけではなく、美容の大敵で老化の原因であるともいわれています。
「秋の夜長」は睡眠改善にうってつけ
睡眠は、身体の機能を整えるのに大切なものにもかかわらず、どうしても疎かにされがちです。実は、乱れた睡眠習慣を改善する一番良い季節が「秋」だと言われています。
中医学では、春から夏に向けて身体全体の働きが活性化する(陽)、秋から冬にかけて沈静化する(陰)、と考えます。血流・消化吸収・新陳代謝などの身体の機能は、春から活動的になり、夏に最も活発化します。だからたくさん身体を動かし、時には少々夜更かししても、新たな活力がすぐ湧いてきます。一方、秋から冬に向けては活力が低下するので、睡眠は「早寝」が基本。夕暮れが早まり、夜が長くなってくる自然のリズムに合わせて、寝る時間を早め、睡眠時間を長くすることが大切。
長い夜にはしっかり睡眠をとって毎日こまめに疲れをリセットし、健康を維持する事が中医学における「秋の夜長の過ごし方」です。
「秋の夜長」と言われるように、夏に比べて日照時間が少しずつ短くなります。覚醒と睡眠を切り替えてくれる「メラトニン」という睡眠ホルモンが出やすくなり、睡眠改善を促します。
動物の中には、熊など冬眠するものがいます。これは、寒くなったからではなく、日が短くなってきたことを体内時計が感じているのです。もちろん人間は、冬眠はしませんが、体内時計の働きにより、日の長さに応じて睡眠の状態が変化しています。そして、「春眠暁を覚えず」という言葉もある通り、睡眠の量や質は季節によって違ってきます。
睡眠の状態が変化する要因
季節による日の出と日没の時間差
私たちの人間の睡眠は生体リズムとしての一面をもっていますが、この日の出と日没の時間が、季節によって変化することで、睡眠内容が変わります。季節による温度差
室温やベッド周りの温度が低すぎても高すぎても睡眠に悪影響を与えます。
眠りと体温の関係性
「睡眠力」を養うための基本体温は睡眠と深い関係があります。
体温は睡眠と深い関係があります。私たちの身体には、活動する日中には体温を高く保ち、就寝時には身体の内部の温度(深部体温)を下げることで、脳と身体をきちんと休息させる仕組みが備わっています。眠気が訪れるのは、皮膚表面から熱を逃がし、深部体温が下がり、それに伴って身体が休息状態になるからです。ちなみに、深い睡眠の時ほど、体温は大きく低下します。
そして、熱を逃がすのに重要な働きをしているのが、手足の特に甲の部分です。赤ちゃんの手が温かくなるのは「眠くなるサイン」ですよね。それは、そこから熱を逃がしているからです。
冷え性の人が、不眠になりやすいのは、手足から熱が放出されにくく深部体温が下がらないからです。質の良い睡眠がとれないと、自律神経の働きが乱れて血行が悪くなり、ますます身体が冷えるという悪循環に陥ってしまいます。
さいごに
寝る時間がもったいないと考える方もいるかもしれませんが、身体を回復させ、日中を快適に過ごし、今もこれからも健康を維持するために、睡眠をしっかりとってください。また、お食事も、生きるために必要な時間です。食事と睡眠の時間を先に取り分けてから、人生を楽しく過ごすための習慣をぜひつくりましょう。