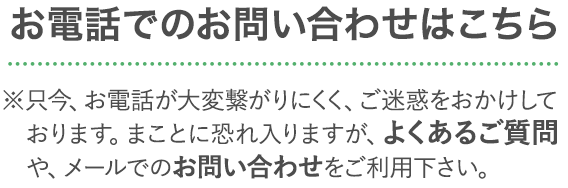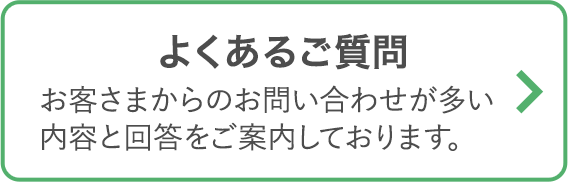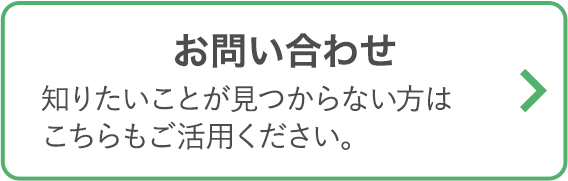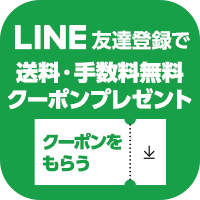楊さちこの季節のコラム
夏の養生法
2020.06.30

そろそろ本格的な夏が来ます。今回は、本格的な夏を快適に過ごすための「夏の養生法」をお伝えいたします。
人間と自然とが寄り添うことが健康の秘訣と考える中医学では、立夏から立秋までを『夏』と考えます。
(今年のカレンダーでいうと5月5日から8月6日まで→これは中国で作られた陰暦を基準にしているからです)
1年を24等分した陰陽思想
陰暦は農作業の目安にするため、1年を24等分して季節の特徴を表したものです。その基礎となっているのは陰陽思想です。
1年を陰陽の変化として見ると、
- 陽気が次第に盛んになって陰気は衰えていく
- 陽気が極になって衰え始め、陰気は次第に盛り返し始める
- 陰気が次第に盛んになって陽気は衰えていく
- 陰気が極になって衰え始め、陽気は次第に盛り返し始める
となります。

自然界はすべてが互いに影響を与え合いながら存在しています。その基礎となっているのが、「あらゆるものは陰と陽の関係性の上に存在している」という考え方です。私たち人間も、絶えず自然環境の影響を受けながら体内の陰陽のバランスは常に変化しています。健康であり続けるため、病気から快復するためには、こうした周囲の環境にも配慮しなければなりません。
“夏”の特徴
陰暦の夏には、1年を24に分けた中の6つの節気があります。順にご紹介しましょう。
立夏(りっか)5月5日
山野に新緑が目立ちはじめ、風もさわやかになって、いよいよ夏の気配が感じられる頃です。
小満(しょうまん)5月20日
草木が茂って天地に満ち始めるという意味。陽気が盛んで、田に苗を植える準備を始めるなど、万物がほぼ満足する季節といえます。
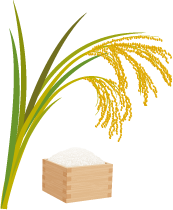
芒種(ぼうしゅ)6月5日
芒種とは芒(のぎ)のある穀物、すなわち稲を植えつける季節を意味しています。この季節、農家はことのほか多忙をきわめます。
夏至(げし)6月21日
昼の長さがもっとも長く、夜の長さがもっとも短い日。農家は田植えに忙しい季節です。
小暑(しょうしょ)7月7日
夏至を境に日脚は徐々につまってきますが、暑さは日増しに加わってきます。

大暑(たいしょ)7月22日
気候的にも梅雨明け後の、もっとも暑気の激しいころ。夏の土用はこの節気に入ります。
【夏の養生法7つのポイント】
一口に夏といっても梅雨時のじめじめした気候や盛夏の酷暑までいろいろですが、夏の養生法の基本原則は、暑さや湿気から身を守ること。そのためのポイント7つが以下の通りです。
1 気を使うより身体を使いましょう

取り越し苦労も、過ぎたことをクヨクヨ考えるのも身体にはよくありません。運動をしてストレスを汗とともに流しましょう。早足の散歩もおすすめです。
2 冷房はほどほどに

クーラーの調節には気を付けて、できれば自然のままが一番よいのです(外との温度差は5℃まで)。夏の暑いときは、長時間冷房の部屋に居続けたり、絶えず冷たいものを飲んだり、風に当たったまま転寝したりすると夏風邪をひきやすくなります。風邪の原因である風寒の気が人体に入ると、四肢が麻痺したり腰や膝が痛くなったりという症状を引き起こします。高血圧や狭心症、動脈硬化、心筋梗塞などの持病のある人が、夏にこうした寒冷の刺激を受けると、血管が痙攣して血圧が上昇し、持病を再発させたり悪化させてしまいます。夏だからこそ「冷え」に用心が必要です。
3 ビールや清涼飲料などの飲み過ぎに注意

お酒の適量は個人によって異なりますが、翌日に残らない程度に、暑いからと言って水分の取り過ぎには気を付けましょう。
4 楽しく食べる

家族そろって楽しい会話の中で食べれば、食欲も進み、消化にもよいものです。食卓では明るい話題で心の栄養を取りましょう。
5 自然を食べる

自然のものをそのままに食べることが、身体には一番いいのです。加工・合成品(インスタントもの)はなるべく避けて、新鮮なものをおいしく食べましょう。
6 夏の旬を食べる

夏野菜として代表的なものは、キュウリ、トマト、ナスなど。どれも身体をさます食性(涼性)をもっています。身体が熱くなりがちで、ノドが乾き胃腸が弱って、食中毒などを起こしやすい。夏を乗り切るのに最適な食品をもっと活用しましょう。
7 休養も忘れず

暑い夏は夜になっても気温が下がらず、睡眠の妨げになります。夏は昼が長く、汗をかいて体力の消耗が激しくなりがち。15〜20分程度の昼寝なら夜の睡眠の妨げにならず、不足した睡眠を補ってくれます。
この7つを心に留めていただけたら、心も身体も快適な夏を過ごしていただけるはずです。