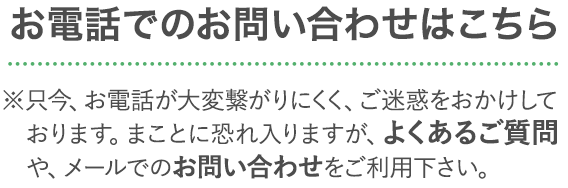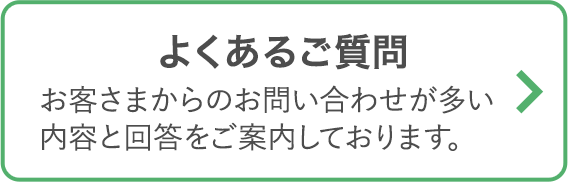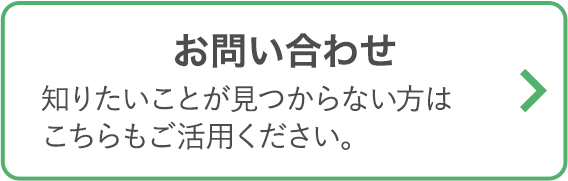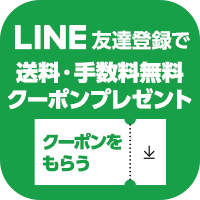楊さちこの季節のコラム
梅雨時季を健やかに過ごす方法
~生活や身体の中の余分な水分を「除湿」~
2021.07.01

今年の梅雨入りは各地で記録的に早くなりました。「梅雨」と聞くと、湿気によりジメジメした蒸し暑さや雨が降ることで予期せぬ肌寒さを感じることもあり梅雨特有の体調不良を感じる方も多くなります。そこで重要なのが「余分な水分を溜めないこと」。今回は、梅雨時季を心身ともに健やかに過ごす方法をご紹介します。
梅雨時季の不調の向き合い方と夏を迎える前の準備
「梅雨」と聞くだけで、じとじとジメジメから始まる不調を思い浮かべて憂鬱になる方も多いと思います。
中医学では、病気を引き起こすものを「邪気」といいますが、その中には、身体の外からもたらされる「六淫」(風邪、寒邪、湿邪、燥邪、暑邪、火邪)と、身体の内から生じる「内生五邪」(内風、内寒、内湿、内燥、内火)があります。そのうち、梅雨の季節の不調の原因になりやすいのが、「湿邪」と「内湿」です。
「湿邪」とは
「湿邪」は、大気中の湿気が口や鼻、皮膚などを通じて身体に入りこむと、体内の余分な水分を貯め込みます。「湿邪」が貯まると、汗を作る機能が低下するので体温が奪われ、冷えや下痢、むくみや頭痛、めまい、食欲不振、湿疹などさまざまな症状を引き起こす原因になります。
「内湿」とは
「内湿」とは主に、乱れた食生活でおなか(中医学では脾胃といいます)が冷えて湿気がたまることで、食欲不振や下痢、軟便など、身体にさまざまな不調が生じることをいいます。胃腸が弱くなると全身の水の巡りはさらに悪くなりさらに余分な水が溜まります。余分な水が溜まると、よけいに身体が冷え、血液の循環が滞って代謝が悪くなり、 汗や尿で水分をしっかり排出できなくなります。そしてさらに、身体に余分な水が貯まることになります。
この悪循環を断ち切るためにすること。それは、【除湿】です。
①家の除湿
雨が続くときは、降っている間は窓を閉めて湿気を入れないようにし、晴れたら窓を開けて風を通すようにします。部屋の湿度を40~60%に保つように、除湿したり乾燥剤を置いたりします。
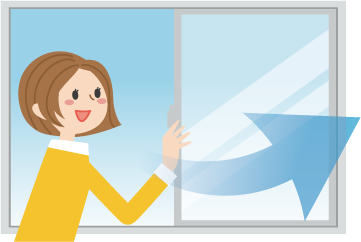
②お出かけ時の除湿
お出かけするときは雨に濡れないようにし、濡れたときはできるだけ早く拭き取って乾かします。
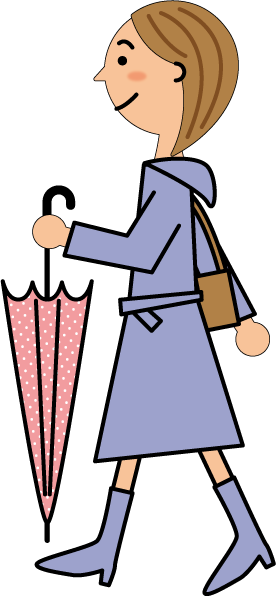
③食事で除湿
体内の余分な水分を汗や尿で排出しやすい状態にしましょう。唐辛子やカレー粉は発汗を促します。しょうが・ ニンニク・ねぎ・ニラ・みょうが・大葉・ミント など、この時期の「香りのする野菜」は消化力を強め、身体を温めて代謝を上げます。夏野菜は利尿作用があるものが多いのですが、生で食べると身体を冷やすので、加熱調理をお勧めします。 生もの・冷たいドリンクなどの摂り過ぎには注意してください。

④下半身を温めて除湿
水は下に溜まるので、『湿邪』の症状は下半身のむくみなどになってあらわれます。全身の血流をよくするためにも、靴下やスパッツの重ね履きなど、とにかく下半身をしっかり温めてください。冷房の風に直接あたらなければ上半身は薄着でも大丈夫。暑いときは上半身の衣服で調節しましょう。
⑤バスタイムで除湿
夏でもシャワーですませないで湯船に浸かるのがお勧めです。ぬるめの半身浴はリラックス効果で自律神経を整え、ストレスや痛みを軽減します。
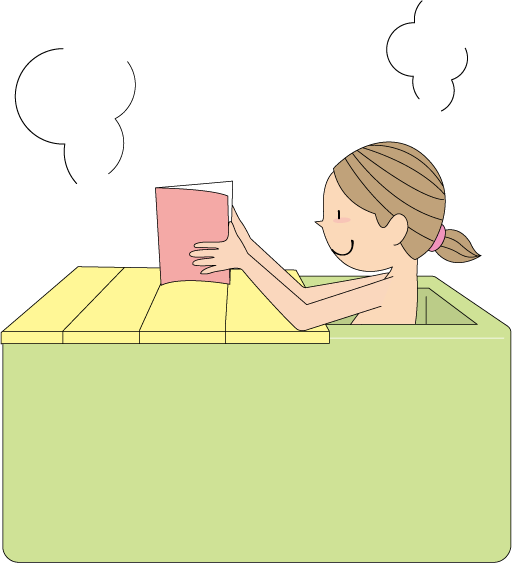
⑥ウォーキングで除湿
ウォーキングやストレッチで、汗をかく習慣をつけましょう。

「除湿」だからといって、「水を飲まない」のはダメです。水を飲まないと、逆に身体が巡ってくれません。十分な水分補給をすることで、しっかり除湿できる身体になれるんです。
除湿習慣を身につけて梅雨から始まる暑い夏を健やかに過ごしましょう!